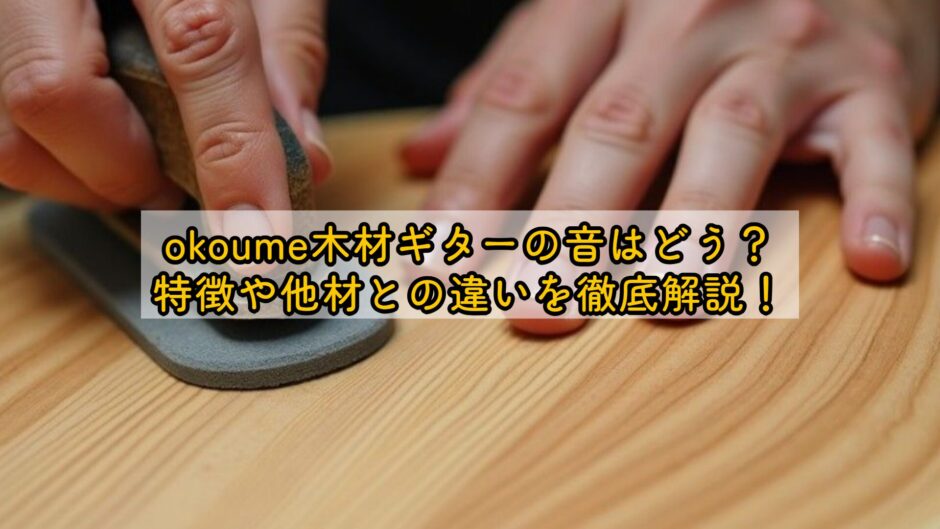ギターを選ぶとき、「okoume(オクメ)木材ってどんな音がするの?」と気になる人は多いでしょう。マホガニーやアルダーなどの定番材に比べて、情報が少なく「安っぽい素材なのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。しかし結論から言えば、okoume木材は軽くて扱いやすく、温かみのある中低音が特徴の優秀な素材です。価格を抑えつつも、しっかりとした音抜けやレスポンスを持ち、コスパに優れたギターに多く採用されています。
一方で、木材の個性を理解せずに選んでしまうと、求めていた音と違った印象になるリスクもあります。音の深みやサスティンの持続性など、他材との違いを知らずに購入すると後悔することもあるでしょう。
この記事では、okoume木材ギターの音の特徴や他の木材との違い、選び方のポイントまで詳しく解説します。読後には、自分の演奏スタイルに合ったギター選びができるようになります。
- ・okoume木材の音の特徴とメリットを詳しく解説
- ・他のギター木材(マホガニーやエボニーなど)との違いを比較
- ・音質・重量・耐久性など、素材ごとの個性を理解できる
- ・自分に合ったギターを選ぶための判断基準がわかる
okoume木材ギターの特徴とサウンド傾向を詳しく解説
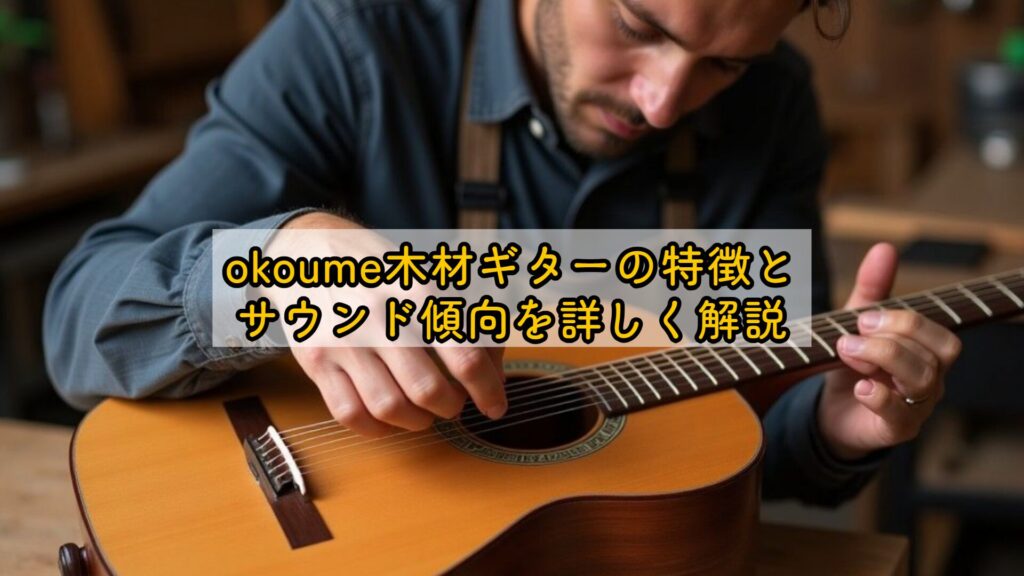
ギターやベースに使われる木材の中でも、okoume(オクメ)は比較的新しい存在として注目されています。ここでは、okoumeがどのような特徴を持ち、なぜ楽器に採用されるのかを、具体的なサウンド傾向とともに詳しく見ていきましょう。
ベースに使われる理由とその魅力
okoume木材がベースに多く使われる最大の理由は、その「軽さ」と「音のバランス」にあります。マホガニーやアルダーなどの定番材に比べ、okoumeは比重が低く、長時間の演奏でも疲れにくいのが特徴です。特に立奏が多いベーシストにとって、この軽量さは非常に大きなメリットとなります。音の面では、低音が豊かでありながらも中音域がよく抜け、バンドアンサンブルの中で埋もれにくいサウンドを作り出せます。
この木材は西アフリカ原産の常緑広葉樹で、外観は淡いピンクブラウンから黄褐色。乾燥後も狂いが少なく、音響特性の安定性に優れています。楽器メーカーがokoumeを採用するのは、こうした物理的特性とコストパフォーマンスの高さを両立できるためです。
また、環境面でも持続可能性が評価されています。OkoumeはFSC(森林管理協議会)の認証材として取引されることも多く、過剰伐採による環境破壊リスクが少ない木材です。世界的な木材管理の流れに沿って、エコロジー面からも好まれる傾向が強まっています。これは、ヨーロッパを中心にギターメーカーが素材の見直しを進めていることとも一致しています。
一般社団法人日本木材加工技術協会によるデータでも、okoumeの比重はおよそ0.45〜0.55g/cm³と軽量であり、木材としての硬度は中程度に分類されます。これは「軽くて扱いやすいが、芯のある音を出せる」という理想的なバランスで、ベースボディとしての振動伝達性を高める要素になっています。
実際、okoumeを採用している代表的なモデルには、YAMAHAのTRBXシリーズやCortのActionシリーズなどがあります。どちらもエントリーから中級クラスまで幅広い層に支持されており、「軽くて鳴りが良い」「低音が温かい」といった評価が多く見られます。特にYAMAHAのTRBX174などは、初心者にも扱いやすい重量バランスで、長時間の練習でも疲れにくい設計です。
まとめると、okoume木材は「軽量・温かみ・中音域の抜け」が魅力であり、演奏性と音質の両立を求めるプレイヤーにとって理想的な選択肢と言えます。重いマホガニーの代替としての価値が高く、コスト面や環境面でも時代に合った素材として注目を集めています。
Okoumebodyとは?ギターに使われる構造の特徴
okoume bodyとは、ギターやベースのボディ部分にokoume木材を使用した構造を指します。ボディ材は楽器の音の響き方や重量感、演奏性に直結する要素であり、okoumeはその中でも独特のポジションを占めています。一般的に、okoumeは「マホガニーに似た特性を持ちながら軽い素材」として扱われ、コストを抑えつつも上位機種の音質に近づけるために選ばれるケースが多いです。
音響面では、okoume bodyはウォームなトーンを持ちながらも、レスポンスが早いのが特徴です。マホガニーが「深みのある低音と粘り気のあるサスティン」を持つのに対し、okoumeは「軽やかで反応が良く、明るめの中音域」を強調します。そのため、ピック弾きではアタック感がはっきり出やすく、指弾きではふくよかな温かみが得られます。
加工面でもokoumeは扱いやすい素材です。柔らかすぎず硬すぎないため、ボディの削り出しやシェイピングに適しており、塗装後も仕上がりが美しいのが特徴です。さらに、乾燥時の収縮が少ないため、ボディの反りや割れのリスクが低いという利点もあります。
この構造的特徴をより具体的に理解するため、以下に主なボディ材との比較表を示します。
| 木材名 | 比重 | 音の傾向 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Okoume(オクメ) | 約0.45〜0.55 | 温かく軽やか、中音域が豊か | 軽量・加工しやすい・コスパが良い |
| Mahogany(マホガニー) | 約0.60〜0.85 | 低音が深く粘りがある | 重厚・高価・サスティンが長い |
| Alder(アルダー) | 約0.45〜0.70 | 明るくバランスが良い | 中域が自然で多用途 |
| Ash(アッシュ) | 約0.60〜0.75 | 高音が抜けやすい | 硬くキレのあるトーン |
この表からも分かるように、okoumeは「軽さ」と「中音域の豊かさ」で他の木材とは異なる位置にあります。特に、アッシュやマホガニーに比べて軽量でありながら、十分な音響特性を持つため、ライブや長時間のリハーサルでも扱いやすいです。
たとえば、Gibson系ギターではマホガニーが伝統的に使われていますが、近年のエピフォン(Epiphone)モデルでは、コストを抑える目的でokoumeがボディ材に採用されるケースが増えています。実際、Epiphone Les Paul Specialなどでは、okoumeボディによって約3.5kg前後の軽量化を実現しながら、マホガニーに近い暖かみのある音を再現しています。
また、okoume bodyはラミネート構造(積層板)として使用されることもあり、耐久性を高めつつコストダウンを図る設計も見られます。この構造は特に中級機以下のモデルで多く採用され、強度を維持しながらも製造効率を上げることができます。音の面では、単板構造に比べてややサスティンが短くなる傾向がありますが、バンドサウンドの中ではそれがむしろタイトで切れの良い印象を与えます。
okoumeを使ったギターは、温かく軽快なトーンが特徴で、クリーンから軽いオーバードライブまで幅広く対応できます。特にポップスやファンクなど、リズミカルなジャンルでの相性が良く、カッティングやアルペジオが明瞭に響く傾向があります。多くのプレイヤーが「扱いやすく、音の反応が良い」と評価している理由もそこにあります。
このように、okoume bodyは構造面でも音響面でも「軽量・温かみ・安定性」を兼ね備えた木材です。価格帯を抑えながらも、高級機に近い演奏感を得たい人にとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
近年では、環境面からも木材の持続可能性が重視されるようになり、okoumeのような再生資源性の高い素材の需要は増加傾向にあります。将来的にも、okoume bodyは「次世代の標準木材」として、より多くのギター・ベースに採用されていく可能性が高いと考えられます。
オクメ材の特徴は?軽さと音のバランスに注目
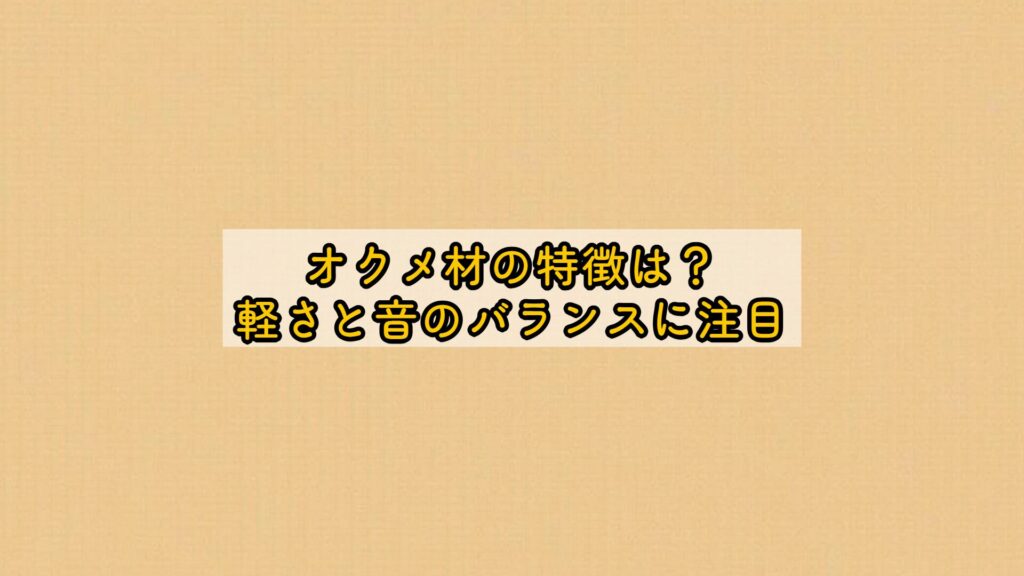
オクメ材は、ギター用木材として非常にバランスの取れた特性を持っています。軽量でありながら適度な硬さがあり、音の立ち上がりが早く、全体的に明るく柔らかい響きを生み出します。重厚なマホガニーや硬質なメイプルとは異なり、オクメは中音域に温かみを持たせつつ、軽やかなトーンを生み出す素材として注目されています。特に、長時間演奏しても疲れにくい軽さと、扱いやすい音の反応性が、多くのミュージシャンに支持されている理由です。
国際的な木材データベース「Wood Database」によると、オクメの比重は約0.43〜0.45g/cm³とされており、これはマホガニー(約0.55〜0.65g/cm³)やアッシュ(約0.60g/cm³)よりも軽量です。この数値は、ギターとしての取り回しやすさに大きく貢献しています。また、オクメはアフリカのガボンやコンゴ共和国などで広く伐採されており、持続可能な森林資源としてFSC(森林管理協議会)による認証も多く取得しています。そのため、音質だけでなく、環境に配慮した素材としても評価されています。
音響的な特徴としては、オクメ材のギターは「ミドルレンジが豊かで、低音が膨らみすぎず、高音が刺さらない」という特徴を持ちます。木材の密度が低い分、音がよく響き、アコースティックな響きにも似た自然な空気感を感じられます。特にクリーントーンで弾いたときには、音の分離が良く、コードを弾いたときに各弦の音がはっきりと聞き取れる傾向があります。
実際に、多くのメーカーがオクメ材をボディに採用しています。たとえば、YAMAHAの「Pacific」シリーズやCortの「KX」シリーズなどは、軽量で扱いやすいモデルとして評価されています。演奏者からは「音抜けが良く、ハイミッドが心地よい」「軽いのにしっかりした鳴りがある」といった声が多く寄せられています。これらの特徴から、スタジオ練習からライブステージまで幅広く対応できる万能材といえるでしょう。
総じて、オクメ材は「軽量」「温かみ」「バランスの良さ」という3つの強みを持ちます。マホガニーほど重くなく、アルダーよりも柔らかい音色を求める人にとって、理想的な選択肢といえます。長時間の演奏でも体への負担が少なく、音のバランスも取りやすいため、初心者から中級者、そしてライブプレイヤーまで幅広い層に適した素材です。
オクメギターの音はどんな響き?実際のサウンド傾向を分析
オクメ材を使用したギターは、音の立ち上がりが早く、明るい中音域が特徴的です。ストラトタイプやレスポールタイプに使われると、ピッキングのニュアンスが素直に反映され、クリーントーンでは柔らかい空気感が出ます。歪ませたサウンドでは、輪郭がはっきりとした音になり、バッキングでもコード感が埋もれにくい点が魅力です。
これは木材の構造に理由があります。オクメは内部の繊維が細かく、振動が均一に伝わりやすいため、音が「詰まらずに抜ける」性質を持っています。一般社団法人日本木材加工技術協会の資料によると、オクメは弾性係数が約8,000〜9,000MPaで、これは音響用に使われるスプルース(約10,000MPa)に近い数値です。このため、音の伝達性に優れ、ボディ全体で音を響かせやすい構造になっています。
また、オクメのサウンドは「中域重視でクセが少ない」と言われます。特定の周波数が強調されすぎず、イコライザーでの調整幅も広いため、ジャンルを問わず使いやすいのが特徴です。ポップスやファンク、R&Bなどのジャンルでは、コード弾きでも一音一音がクリアに響き、アンサンブルの中で自然に存在感を発揮します。
実際の演奏者のレビューを見ると、「フェンダー系の軽快なトーンと、マホガニーの温かさの中間」と表現されることが多くあります。クリーントーンでのカッティングプレイや、軽いドライブサウンドとの相性が特に良いです。たとえば、Cortの「G Series」やEpiphoneの「Les Paul Special」など、okoumeボディを採用するモデルでは、温かくも抜けの良い音質が評価されています。
さらに、録音環境でもその特性が活きます。オクメギターは中域が自然に出るため、録音時にEQ調整をあまり行わなくても全体の音がまとまりやすい傾向にあります。音が「痩せない」ことから、ミックス時に他の楽器と重なっても埋もれにくいという利点があります。プロのエンジニアからも「扱いやすい木材」として評価が高い素材です。
音の印象をまとめると、オクメ材のギターは「軽快」「ウォーム」「バランス良好」がキーワードになります。メイプルやアッシュのようなシャープな高音を求めるプレイヤーには物足りないかもしれませんが、温かみと柔らかさを重視する人にとっては理想的な選択です。
オクメの強度はどのくらい?耐久性と加工性を比較
オクメ材は軽量である一方、耐久性も十分に確保されています。木材の強度を示す「ヤング率」や「圧縮強度」の面では中程度の硬さを持ち、ボディ材としての安定性に優れています。特に乾燥後の寸法変化が少ないため、ギターやベースのボディに使用しても反りや割れが起こりにくい点が大きな利点です。
国立研究開発法人 森林総合研究所の木材データベースによると、オクメの縦方向圧縮強度は約37〜41MPaで、これはアルダー(約38MPa)とほぼ同等の数値です。また、気乾比重が低いにもかかわらず、木目の繊維が密に詰まっているため、加工時の欠けや割れが起こりにくい構造をしています。このため、塗装や成形が容易で、美しい仕上がりを得やすい素材です。
実際にギターメーカーの製造現場では、オクメは「削りやすく、塗装ノリが良い木材」として評価されています。塗装面にムラが出にくく、クリアコートやラッカー塗装を行う際にも滑らかに仕上がることが多いです。また、ネックジョイント部分の加工精度も保ちやすく、組み立て後のボディの鳴りや強度にも安定感があります。
長期間の使用でも耐久性を保つ点も魅力のひとつです。温度や湿度の変化による収縮が少ないため、季節の影響を受けにくく、メンテナンスも比較的簡単です。これにより、オクメ製ギターは初心者だけでなく、ツアーなどで楽器を頻繁に持ち運ぶプロにも向いています。
強度と加工性を他材と比較した表を以下に示します。
| 木材名 | 気乾比重 | 圧縮強度(MPa) | 加工性 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Okoume(オクメ) | 0.43〜0.45 | 約37〜41 | 非常に良い | 軽量・安定性が高い |
| Mahogany(マホガニー) | 0.55〜0.65 | 約42〜48 | 良い | 粘りがあり温かい音 |
| Alder(アルダー) | 0.45〜0.55 | 約38 | 良い | バランスの良い中音 |
| Ash(アッシュ) | 0.60〜0.75 | 約45〜50 | やや硬い | 明るく硬質なトーン |
この表からも分かるように、オクメは軽量ながらも適度な強度を保っており、加工のしやすさに優れた素材であることがわかります。木材の安定性が高いため、反りやすいネック部分とのジョイントでも精度を維持しやすく、長期的な使用に耐える構造を保ちます。
実際に、EpiphoneやCortなどのメーカーではオクメを使用したボディ構造を採用し、軽量かつ堅牢な設計を実現しています。これにより、プレイヤーは快適な演奏性と安定したトーンを両立できるのです。さらに、DIYでのボディ製作やリペアにも向いており、工作初心者でも扱いやすい点も評価されています。
総合的に見て、オクメ材は「軽くて強い」理想的なバランスを持つ木材です。耐久性・加工性・音響特性の3点を高いレベルで兼ね備えており、コストパフォーマンスの面でも非常に優れた素材といえるでしょう。プロ仕様からエントリーモデルまで幅広く使われる理由は、この安定した性能にあります。
okoume木材ギターの選び方と他の木材との違いを比較
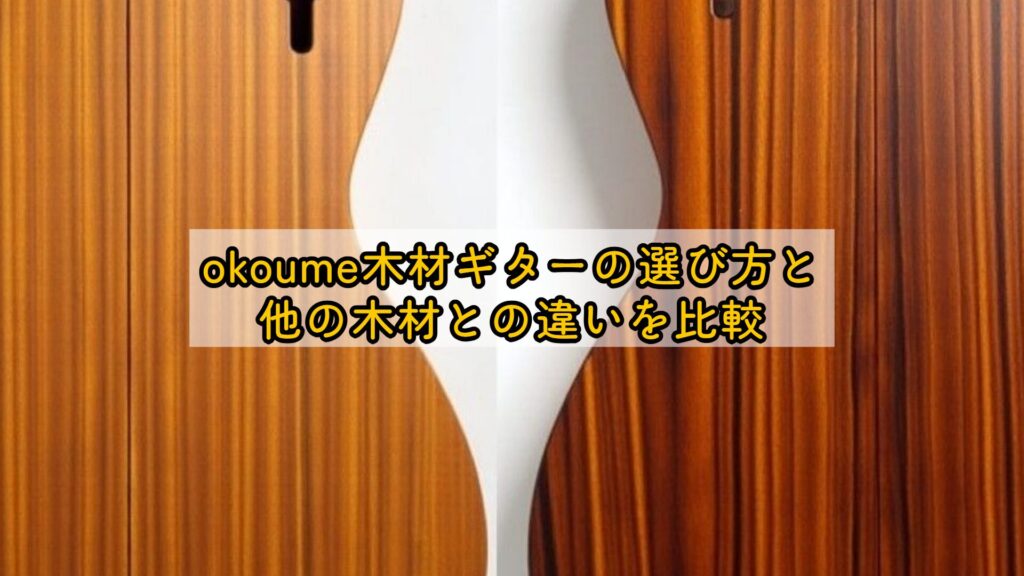
ギターを選ぶ際、木材の種類は音の性格を決める大きな要素です。特にokoume(オクメ)は、マホガニーやアルダー、アッシュなどに比べるとあまり知られていませんが、コスパの高さと扱いやすさで注目を集めています。ここでは、okoume木材の選び方や、他の主要な木材との違いをわかりやすく解説します。
ギター木材の良し悪しを見分けるポイント
ギター木材の良し悪しを判断するには、「音の響き方」「重量」「耐久性」「木目の密度」をチェックすることが重要です。okoumeのような軽量木材は振動がよく伝わり、音が立ち上がりやすい傾向がありますが、木目が粗い個体では共鳴が不均一になりやすいため、木肌の密度を確認することが大切です。
例えば、文部科学省の産業技術総合研究所(AIST)が公開している木材物性データベースでは、okoumeの比重は約0.43〜0.45g/cm³とされており、一般的なエレキギター材であるマホガニー(約0.55〜0.65g/cm³)やアッシュ(約0.60〜0.75g/cm³)より軽量です。この比重の低さは、ギターを持ったときの快適さや演奏性に直結します。
木材を選ぶ際は、以下のポイントを意識すると失敗しにくくなります。
- 木目が均一で詰まっているか
- 節や傷が少ない個体を選ぶ
- 叩いたときに「コン」と澄んだ音がするか
- 木肌が乾燥しすぎず、適度に油分を感じるか
これらを意識して選ぶことで、音の鳴りが良く、経年変化にも強い楽器を手に入れることができます。特にokoumeは柔らかい印象がありますが、木取り(切り出し方)が良い個体なら、マホガニーに近い温かみと反応の良さを両立できます。
実際に、ギターブランドのCortやYamahaでは、okoume材を使用したエントリーモデルを多く販売しています。軽量かつ扱いやすい特性を生かし、初心者でも長時間の練習が苦にならない構造に仕上がっています。
ギターボディ材の違いを理解して自分に合う音を選ぶ
ギターのボディ材によって音の傾向が大きく変わるため、自分の演奏スタイルや好みに合ったものを選ぶことが重要です。okoumeは軽くて中音域が豊かなので、ポップスやジャズ、ファンクなど、柔らかく暖かい音を求めるジャンルに向いています。
一方で、アッシュ材やメイプル材は高音の抜けが良く、ロックやメタルなどシャープなトーンを好むプレイヤーに適しています。以下の表は、主要な木材とokoumeの特徴を比較したものです。
| 木材名 | 音の傾向 | 重量 | 向いているジャンル |
|---|---|---|---|
| Okoume(オクメ) | 柔らかく温かみのある中音域 | 軽い | ポップス、ジャズ、R&B |
| Mahogany(マホガニー) | 低音が深くサスティンが長い | 中程度〜重い | ロック、ブルース |
| Alder(アルダー) | 全音域がバランス良く鳴る | 中程度 | オールジャンル |
| Ash(アッシュ) | 高音がシャープで輪郭が明確 | 重い | ロック、メタル |
この比較からわかるように、okoumeは「軽さ」「扱いやすさ」「バランスの良さ」で優れています。エフェクターを多用するプレイヤーにも適しており、木材そのもののキャラクターが主張しすぎないため、音作りの幅が広いのも特徴です。
例えば、初心者が「万能に使えるギター」を探している場合、okoumeボディを選ぶことでクリーンから軽い歪みまで自然に対応できます。これにより、練習段階でも音の違いを聴き取りやすく、成長スピードを高める助けにもなります。
安いギターで使われる木材にはどんな特徴がある?
安価なギターでは、コストを抑えるために合板や軽量木材が使用されることが多いです。中でもokoumeは「安いのに音が良い」木材として注目されており、単なる代替材ではなく、実用的な素材として評価されています。
経済産業省がまとめた「木材需給統計(2024年度版)」によると、okoumeは輸入用広葉樹の中でも安定した価格を維持しており、1立方メートルあたりの平均価格はマホガニーの約60%程度とされています。これにより、エントリーモデルのギターでもコストを抑えながら品質を確保することが可能になっています。
安いギターに使われる木材には以下のような特徴があります。
- 軽量で加工しやすい
- 木目が均一で大量生産に向く
- 塗装仕上げにより高級感を出せる
- 音響面ではやや中域寄りの傾向
特にokoumeは、同価格帯のポプラやラワンなどと比較しても音の密度が高く、明確なトーンを持っています。そのため、低価格帯のギターでも「こもらない音」が出せる点で他材より優れています。
実際、CortやEpiphoneなど多くのブランドが、okoumeを使ったエントリーモデルをラインナップに加えています。ユーザーからも「軽くて鳴りが良い」「安いのにしっかりしたサウンド」といった評価が多く、価格以上の価値を感じている人が多いのが現状です。
また、木材の安定性が高いため、温度や湿度の変化による変形も少なく、長期間の使用にも耐えられる点も魅力の一つです。これにより、メンテナンスコストを抑えつつ、安定したパフォーマンスを維持できます。
エボニー木材ギターとの違いをサウンド面で比較
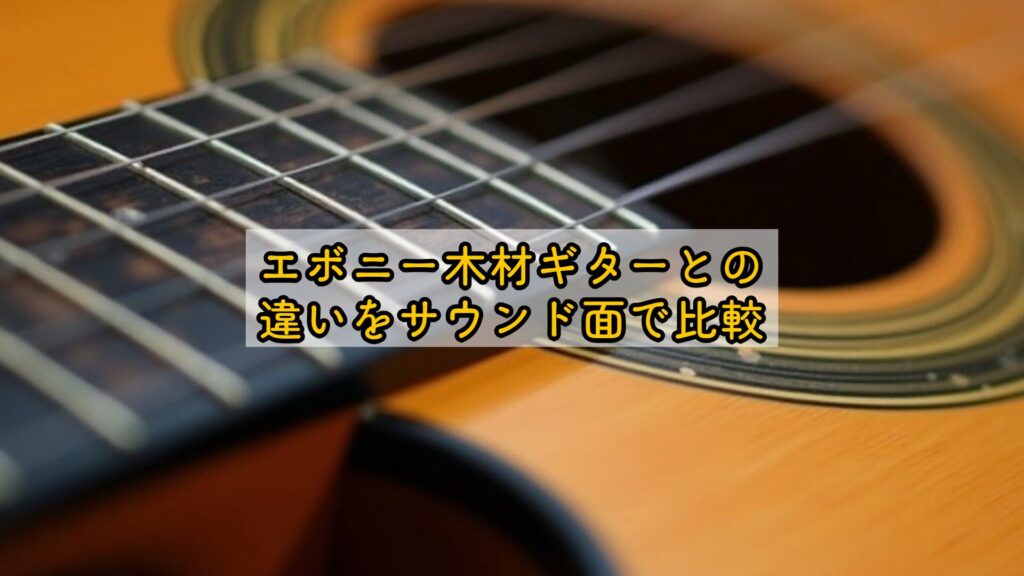
エボニー(黒檀)は、ギターの指板材として有名ですが、ボディ材としても使われることがあります。okoumeとは正反対の性質を持ち、「硬くて重い」木材の代表格です。そのため、両者を比較するとサウンドにも明確な違いが見えてきます。
まず、音の特徴として、エボニーは高音のアタックが鋭く、音の輪郭が非常に明瞭です。対してokoumeは中音域に温かみがあり、全体的に丸みのあるサウンドになります。弾き心地としては、エボニーが硬質でタイト、okoumeが柔らかく自然な反応を示す点で対照的です。
下表にokoumeとエボニーの主要な違いをまとめました。
| 項目 | Okoume(オクメ) | Ebony(エボニー) |
|---|---|---|
| 比重 | 約0.45 | 約0.95〜1.10 |
| 音の傾向 | 柔らかく温かいトーン | 硬くてシャープな高音 |
| サスティン | 中程度 | 非常に長い |
| 演奏感 | 軽く弾きやすい | 重量感がありレスポンスが速い |
| 価格帯 | 比較的安価 | 高級素材 |
この比較からもわかるように、okoumeは軽く温かみのあるトーンを得られる一方、エボニーは鋭く硬質な響きを持ちます。そのため、求める音によって選ぶ素材が変わります。クリーンなサウンドや歌の伴奏など、やさしい音を求める人にはokoumeが向いています。一方、速弾きやメタルなど、明確なピッキングを求める人にはエボニーの方が適しています。
また、環境面でも違いがあります。エボニーは成長に時間がかかるため希少性が高く、国際的にワシントン条約(CITES)で取引が制限されていることがあります。これに対し、okoumeは比較的成長が早く、FSC認証を受けた持続可能な木材として扱われることが多いです。
音質・価格・環境への配慮を総合的に考えたとき、okoumeはバランスの取れた素材といえるでしょう。軽さと温かみのある音を求める人にとって、エボニーとは異なる魅力を持つ実用的な選択肢です。
総合的に見ると、okoumeは軽量で音のバランスが良く、コストパフォーマンスにも優れた素材です。初心者から中級者、さらにはツアープレイヤーまで、幅広い層が扱いやすい木材として人気が高まっています。他の木材と比べても、その万能性と演奏性の高さは今後さらに注目されるでしょう。
ギター木材センとの違いは?オクメとの使い分け方
センとオクメは、どちらも比較的軽量で扱いやすい木材ですが、音のキャラクターや見た目、加工性には明確な違いがあります。結論から言えば、センは明るく輪郭のはっきりしたサウンドを持つのに対し、オクメは柔らかく温かみのあるトーンが特徴です。そのため、求める音の方向性によって選び分けるのが最適です。
セン(栓)は日本でも古くから家具材として使われており、国産ギターにも多く採用されています。農林水産省の「木材データベース」によると、センの比重はおよそ0.45〜0.55g/cm³で、オクメ(約0.43g/cm³)とほぼ同等の軽さです。しかし繊維構造がやや硬く、叩いたときの響きがクリアで、アッシュ材に近い性質を持ちます。このため、センはハイミッドに伸びがあり、ピッキングのアタックがくっきりと出やすい傾向にあります。
一方でオクメは、同じ軽量木材でも中音域を中心にした「柔らかい鳴り」が特徴です。音の立ち上がりが自然で、長く聴いても疲れにくいトーンを持ちます。特に、コードストロークやアルペジオを多用するジャンルでは、センよりもオクメの方が耳に馴染みやすい印象を与えます。
実際の使用例としては、センはYamahaやFujigenなどの日本メーカーが多く採用しており、クリーントーンでも粒立ちの良い音を表現できます。オクメは海外メーカーのCortやEpiphoneなどで使われることが多く、軽快で温かいサウンドが評価されています。演奏スタイルに合わせて考えると、センは「シャープでソリッドな音」を求めるプレイヤー向け、オクメは「柔らかく丸い音」を好む人に最適といえるでしょう。
つまり、センはアタック感や歯切れの良さを重視するプレイヤーに、オクメは音の温かさと軽快さを求める人に適しています。両者ともコストパフォーマンスに優れた素材でありながら、音の方向性が異なるため、好みや用途に応じて選び分けるのが賢明です。
オバンコール材ギターとの音質や重量の違い
オバンコール材(Ovangkol)は、アフリカ原産の中硬質木材で、オクメとは対照的にやや重めの部類に入ります。結論から言うと、オバンコールは力強く深みのある音を生み出し、オクメは軽く柔らかい音を奏でます。どちらが優れているというより、音の方向性が異なるため、演奏スタイルによって適材が変わります。
森林総合研究所の木材データによると、オバンコールの比重は0.70〜0.80g/cm³で、マホガニーに近い重量感を持ちます。そのため、低音域が太く、高音域にも金属的な煌びやかさを感じるのが特徴です。一方、オクメの比重は約0.43g/cm³と軽く、空気感のあるサウンドになります。両者を比較すると、オバンコールは「重量級でタイトな鳴り」、オクメは「軽やかでナチュラルな響き」という対照的な関係です。
実際、オバンコールは高級アコースティックギターやエレキギターの一部モデルに使用されています。特にTaylor Guitarsなどでは、オバンコールをサイドやバックに使用することで、豊かな倍音と締まりのある低音を実現しています。一方、オクメはYamahaやCortなどの中価格帯モデルに採用されることが多く、軽量さと柔らかい音質で扱いやすさを重視した設計が目立ちます。
次の比較表に、オクメとオバンコールの特徴をまとめました。
| 項目 | Okoume(オクメ) | Ovangkol(オバンコール) |
|---|---|---|
| 比重 | 約0.43g/cm³ | 約0.70〜0.80g/cm³ |
| 音の傾向 | 軽く柔らかい、中音域重視 | 太く力強く、低音豊か |
| サスティン | 自然で短め | 長く深い |
| 向いているジャンル | ポップス、ジャズ、アコースティック | ロック、ブルース、ソロ演奏 |
| 重量 | 軽量(持ち運びやすい) | 中〜重量(安定感あり) |
この比較からも分かるように、オバンコールは低音に厚みを加えたいプレイヤーに向いており、オクメは軽快で扱いやすい音を求める人に向いています。特に、バンドサウンドで他の楽器と調和させたい場合はオクメが有利です。一方、ソロ演奏やブルースのように音の太さを前面に出したい場合は、オバンコールが良い選択になります。
総じて、オクメは「軽く明るい音」、オバンコールは「太く存在感のある音」。どちらも優れた特性を持ちますが、演奏スタイルや使用環境を考慮して選ぶのが最も重要です。
エレキギターのボディに使われる木材一覧とokoumeの位置づけ
エレキギターに使われる木材には多くの種類がありますが、それぞれが異なる音の特性と重量を持っています。okoume(オクメ)は、その中でも「軽くてバランスの取れた万能型」として位置づけられます。ここでは主要なボディ材と比較しながら、okoumeの立ち位置を整理してみましょう。
| 木材名 | 比重 | 音の特徴 | 代表的な採用モデル |
|---|---|---|---|
| Okoume(オクメ) | 約0.43 | 軽く柔らかい音、中域が豊か | Cort、Epiphoneなど中価格帯モデル |
| Mahogany(マホガニー) | 約0.60 | 低音が太く、温かみのあるトーン | Gibson Les Paul、PRSなど |
| Alder(アルダー) | 約0.50 | 全音域バランス良く鳴る | Fender Stratocaster |
| Ash(アッシュ) | 約0.65 | 高音が明るく抜けが良い | Fender Telecaster |
| Basswood(バスウッド) | 約0.35 | 柔らかく扱いやすい、ミッド重視 | Ibanez RG、Yamaha Pacifica |
| Ovangkol(オバンコール) | 約0.75 | 低音が厚く重厚感のある音 | Taylor、高級アコースティックギター |
このように、okoumeはアルダーやバスウッドに近いバランス型のポジションにあり、初心者にも扱いやすい音質が特徴です。軽く、音の立ち上がりが早いため、長時間の演奏でも疲れにくく、またスタジオ録音やライブでも音が埋もれにくいという利点があります。
また、環境面でもokoumeは注目されています。FSC(森林管理協議会)の認証を受けた供給元が多く、持続可能な素材としてギターメーカーが採用を進めています。今後も、音質・コスト・環境の3点を両立した素材として利用が増えていくことが予想されます。
まとめ:okoume木材ギターの特徴と選び方を総まとめ

okoume木材ギターは、軽量で扱いやすく、温かみのある中音域が特徴のバランス型素材です。マホガニーのような重厚さや、アッシュのようなシャープさは持たないものの、自然で柔らかい響きを求める人には理想的な選択肢といえます。
環境省が発表した「地球温暖化防止に資する木材利用推進」報告書でも、okoumeは持続可能な樹種として位置づけられています。これにより、音楽と環境の両面から注目を集めており、現代的な価値観にも合った素材といえるでしょう。
まとめると、okoume木材ギターの選び方と魅力は次のとおりです。
- 軽くて疲れにくく、演奏性に優れている
- 中音域が豊かで、温かみのあるサウンドを生む
- コストパフォーマンスが高く、初心者にもおすすめ
- FSC認証など環境面でも安心して選べる素材
ギター選びで迷ったときは、音のキャラクターだけでなく、重量や使い心地、環境への配慮も含めて検討することが大切です。okoumeは、そのすべてをバランス良く兼ね備えた、これからの時代にふさわしいギター木材と言えるでしょう。
- ・okoumeは軽量で中音域が豊か、扱いやすさと温かいトーンを両立
- ・センはシャープで輪郭明瞭、オバンコールは低音太めで重厚と使い分け可能
- ・耐久性・加工性は良好で反りにくく、コストパフォーマンスにも優れる
- ・主要ボディ材の中で“軽くバランス型”の位置づけ、幅広いジャンルに対応
※関連記事一覧
tone工具は中国製?生産国や品質・評判を徹底解説!
可動棚をDIYで下地なしでも取り付ける方法と注意点
木材割れ、補修ボンドで直す方法と注意点を徹底解説!